1990年代、ジャイアント馬場率いる全日本プロレスにおいて、三沢光晴、川田利明、田上明、小橋健太の4人が生み出した「四天王プロレス」。

その特長は、どんな地方会場でも長時間のマラソンマッチで、相手が立ち上がれなくなるまで徹底的に戦うことにありました。
ノンストップで大技を繰り出し合うカウント2.99の攻防から、次第にエスカレートして脳天から垂直に落とす投げ技や、トップロープからの“雪崩式“、場外に落とす“断崖“技が増え、その功罪はたびたびプロレスファンの間で議題に上ります。
●全日本プロレスを襲う変化の波
1990年代初頭、全日本プロレスは天龍源一郎が退団しSWSへ移籍。さらにジャンボ鶴田が内臓疾患の第一線を退き、2代目タイガーマスクの覆面を自ら脱ぎ捨てた三沢光晴が日本人エースの座に着きました。
この時期、第二次UWFがブームを巻き起こし、さらに企業がバックアップする新団体SWSが旗揚げするなど業界内の変化も激しく、老舗全日本プロレスはどのように対抗していくのか、方向性を模索していました。
この頃、プロレスマスコミ、週刊プロレスの編集長ターザン山本氏は「アンチSWS、馬場全日本支援」の姿勢を鮮明にし、それまで頑なにスタイルを変えなかったジャイアント馬場に対して外部からさまざまな団体運営やマッチメイクなどについてアドバイスする関係になっていました(鶴田から三沢へのエース交代を印象付けるピンフォール決着なども、その中で生まれたと言われています)。
その中でジャイアント馬場は、今後の全日本プロレスの姿勢として「ファンの期待と信頼を裏切らない=灰色決着なしの完全決着スタイル」を決意。
長く昭和プロレスの悪しき慣習である凶器攻撃、流血、両者リングアウト引き分け、反則による決着などを極力廃し、リング内でのピンフォールもしくはギブアップで勝負が決する「完全決着」スタイルを、選手に厳命しました。
●プロレスにおける「両者リングアウト、反則による決着」とは
プロレスの灰色決着は、勝敗を決しにくい同格のレスラー同士の言ってみれば救済措置。
負けた方の商品価値に傷を付けず次回に引っ張る興行上の戦略でもありましたが、決着を望むファンからは当然評判が悪く、試合に対する興味を削ぐ諸刃の剣でもありました。
大物同士の一騎打ちは決まって場外に降りてそのまま試合終了になる両者リングアウト、もしくはレフェリーが巻き込まれる反則による不透明決着が頻発。
特に豪華人気ガイジンを多く抱える全日本プロレスは、それが顕著でした。
また、試合時間も蔵前国技館や日本武道館などのビッグマッチを除けば、地方興行では概ね10分から15分位がほとんどでした。
●原点は「天龍革命」
この全日本プロレスの「悪しき慣習」に最初に変化をもたらしたのは、天龍源一郎が起こした”天龍革命”でした。
長州力の新日本Uターンに危機感を覚えた天龍は阿修羅原ら天龍同盟のメンバー達と連日、地方興行でも一切手抜きなしのガチガチの打撃技と、20分超えのマラソンマッチを敢行。
自らエースのジャンボ鶴田に挑んだ「鶴龍対決」でもリングアウトや反則決着を極力避け、ピンフォールやギブアップの完全決着スタイルを貫きます。
それこそが天龍“革命“だったのです。
長くジャイアント馬場、ジャンボ鶴田と豪華ガイジンの対決が売りだった全日本プロレスは長州らジャパンプロレス、そして天龍革命により日本人対決、軍団抗争にシフト。
しかしその柱である天龍、鶴田を相次いで欠くことになり、その運命は後に「四天王」と呼ばれる若手たちに委ねられます。
●四天王 それぞれの歩み
しかしこの「四天王」、最初から期待されていたわけではありません。
全日本プロレスではこれまでも度々、若手の引き上げを狙いさまざまな試みを行なって来ましたが、いずれも不発。“決起軍“と呼ばれるチームを馬場勅命により結成させ、合宿まで行いマスコミにアピールしたもののまったく結果が残せず、「いつまで経っても決起しないので解散」と馬場御大に言われる始末でした。
この中で三沢光晴(1962年生まれ、当時30歳)は越中詩郎としのぎを削るデビュー当時から将来を嘱望され、2代目タイガーマスクにも抜擢されたエリート。
田上明(1961年生まれ、当時31歳)もまた、大相撲で十両になり幕内間近ながら親方との確執からプロレス入りし、その体格から鶴田とタッグを組むなど、言ってみればエリートコースを歩んでいました。
しかし、川田利明(1962年生まれ、当時29歳)、小橋健太(1967年生まれ、当時25歳)の2人は天龍、馬場とタッグを組むなどはありましたが正直、そこまでプッシュを受けたわけではありません。
三沢の足利公大付属高校の後輩でアマレス経験はあるものの大型揃いの全日本にあって体格に恵まれない川田と、アマでの実績もなくサラリーマンから入門してきた小橋は、これまでの全日本プロレスに長く続く慣習では、「顔じゃない」という扱いのレスラーでした。
そのため川田は三沢を、小橋は川田を、田上と川田はお互いを意識し、ライバル視する関係性が生まれ、その切磋琢磨が進化、深化を生み出す関係性となりました。
●超世代軍vs鶴田軍
最初の転機は、天龍離脱によりタイガーマスクから素顔に戻った三沢光晴のブレイク。
三沢は鶴田を下し、川田、小橋らと“超世代軍“を結成して鶴田軍と対戦を重ね、ファンの支持を獲得していきます。この時、田上も決起軍入りする予定でしたが、パワーバランス的に鶴田のパートナーに指名されました。
この時期(1991年4月20日)に後楽園ホールで行われたファン感謝デーの鶴田・田上・淵vs三沢・小橋・菊池の6人タッグマッチ、試合時間51分32秒の激闘は、今なお語り草です。
その後、1992年末に鶴田が肝炎悪化により戦線を離脱。その結果、三沢と小橋、川田と田上がそれぞれタッグチームを結成。
以降の全日本プロレスは、この4人の戦いを中心に展開していくことになるのです。
●四天王プロレスの誕生
彼らの試合が「四天王プロレス」と呼ばれるようになったのは、1993年。
5月の札幌2連戦で川田&田上がゴディ&ウィリアムス組から世界タッグを獲得し、翌日三沢はハンセン 、川田はウィリアムス、田上はスパイビー、小橋はゴディと強豪ガイジンをそれぞれ、シングルマッチで撃破。
そして三沢vs川田の三冠戦、川田&田上vs三沢&小橋の世界タッグ戦が日本武道館の定番になります。
序盤から大技が連発する“ノンストップバトル“、いずれも試合時間が30分を超える“マラソンマッチ“、必殺技が決まっても返す“カウント2.99“、そして顔面、頭部にエルボーやキックを容赦なく叩き込み、急角度のパワーボムやスープレックスの“垂直落下”の攻防で、観客を熱狂の渦に巻き込みます。
この4者が対決した年末の最強タッグ決勝戦は、解説のジャイアント馬場も感動のあまり絶句する程の名勝負でした。
深夜に放送されていた日本テレビ「全日本プロレス中継」で実況の若林アナの絶叫と共に全国に浸透したこの新しいスタイルを、プロレスファンはいつしか「四天王プロレス」と呼ぶようになりました。
1991年頃から新日本プロレスでは武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の「闘魂三銃士」がメインを張って活躍していたことも、関係していたと思います。
●四天王プロレスの功罪
「功」としては、なんといってもどんなカードでもピンフォールもしくはギブアップで決まる完全決着性と、毎試合、30分近い熱闘を繰り広げる長時間性と、大技が連発されることからくる「満足度の高さ」。そのクオリティは世界でも最高峰と評価され、プロレスファンから熱狂的な支持を集めました。
やがてこの中にアマレスからプロレス入りした秋山準が加わり、スタン ハンセン 、スティーブウィリアムスら強豪ガイジン選手との戦いもあり、他団体を圧倒。
90年代の全日本プロレスは、日本武道館を毎回フルハウスにする黄金時代を迎えました。
「罪」としては、フィニッシュホールド(必殺技)のインフレを引き起こしたこと、そしてなによりも選手へのダメージです。
観客の要求に応じ、納得してもらうために、どんどん技の過激さがエスカレートしていきます。もともと大型のレスラーとの対戦で受け身のうまさに定評のある全日本プロレスのトップ同士で、相手が立てなくなるまで技を繰り出し、完全決着を付けるには、それまでタブーとされてきた脳天から落っことす投げ技、さらにはトップロープ、遂には場外の床に相手を叩きつける”禁じ手”を繰り出すしか、やりようがありません。
さらに、他団体に比べマイクアピールやストーリーつくり、入場時の派手な演出をしない全日本プロレスにおいて、さらに過去の天龍革命や鶴龍対決を超えるインパクトを残すには、技の過激さを増していくしかなかった、とも言えます。
その結果、1990年代中盤以降、蓄積したダメージから両者がブッ倒れたまま立てなくなる時間が長くなり、ひたすら大技を繰り出し合うだけの、大味な試合が続いていくようになりました。
●四天王プロレスの終焉
1990年代後半、三沢がマッチメイクなど団体の運営を取り仕切るようになると、リングアウト決着が増えるなど、徐々にそのスタイルに変化が見られるようになります。
スタートから10年近くが経過したこの時点で選手の多くが怪我を抱えており、30代終盤の年齢的にも、この先鋭的なスタイルを続けている事に限界を感じていた事でしょう。
しかし、ビッグマッチでリングに上がると条件反射的に危険技を繰り出し合い、精魂尽きるまで戦い続けるスタイルを変えることはできませんでした。
1999年、ジャイアント馬場が亡くなると団体運営の方針を巡り、かつてから燻っていた元子夫人への不満が爆発。
2000年6月、三沢、小橋、田上は秋山ら他のほとんどの選手と共に離脱し、自らの新団体プロレスリング・ノアを旗揚げ。
川田は淵らと全日本プロレスに残留し、これをもって四天王プロレスは終焉しました。
●ノア旗揚げ後と三沢光晴の”殉職”
ノアになってから、旗揚げ戦では秋山準による“絞め技による秒殺“など、新たな方向性も模索されましたが、三沢、田上、小橋、秋山らが中心となる新設されたGHCヘビー級タイトルマッチでは相変わらず、かつての四天王プロレススタイル同様の過激な攻防が続けられました。
三沢は首、肩、腰、小橋は膝、肘など、いずれも満身創痍。
そして2009年6月、社長でありエースの三沢光晴選手が試合中に斎藤彰敏選手のバックドロップを喰らい、事故死(享年47歳)するという痛ましい出来事が起こります。
死因は頸椎離断。このバックドロップがこれまでより過激だったというわけではなく、長年蓄積したダメージが暴発した結果なのは、誰が見ても明らかでした。
●その後の四天王
川田利明選手は全日本を背負い新日本プロレスとの対抗戦、ハッスルでも活躍し、ノア参戦も果たしますが2010年をもって事実上の引退。現在ラーメン店「麵ジャラスK」を経営しています。
小橋健太選手は現役中に腎臓がんを患ったものの奇跡のカンバック。2013年に引退し、以降はプロレス大会をプロデュースしたり、講演活動などで活躍しています。
田上明選手は2013年に現役を引退し、ノアの社長に。その後相談役を経て退任して、現在はつくば市でステーキ店を経営。2018年には胃がんのため胃を全摘出しています。
●四天王プロレスと棚橋弘至、オカダカズチカ
四天王プロレスは、抑圧された環境下で、純粋に試合のクオリティを高める若さゆえの探求、でした。
当事者である小橋選手も「あの試合の覚悟を、危ないとか頭から落っことすとかだけで片付けられるのはたまらない」と発言しています。
しかし、凶器なしのハードコア、極北とも言えるその究極のプロレススタイルは観客の支持を集める一方で、当時から「いつか取り返しのつかないことになるぞ」、「(この形式は)単なるタフマンコンテストで、プロ”レスリング”じゃない」と、往年のレスラーからも批判の声があったのも事実です。
中でも必殺技が一発で決まらないカウント2.99スタイルは、より過激に受け身の取れない脳天から垂直落下させる技の攻防につながり、技のインフレ現象を引き起こしました。
現在もこのスタイルに影響を受け、同じように”アタマから落っことし合う”技を連発するレスラーが、世界中に溢れています。
この流れと異なるスタイルとしては、たとえばワールドワイドで業界をリードするWWEでは選手ごとにフィニッシュホールド(必殺技)が明確に決められていて、「まともにくらった必殺技は返してはいけない」という不文律が存在しているように見えます。
また、現在の新日本プロレスの棚橋弘至、オカダカズチカらもこの路線に近い、クラシカルな試合展開を得意にしています。
彼らは試合のクオリティは高めつつも、狙いを一点に定めて集中攻撃する殺人フルコースから、最後は必殺技が一発で決まるという、かつてのプロレススタイルへの原点回帰に近いスタイルです。かつて、ケニーオメガが活躍した際に、棚橋選手はその過激な試合スタイルを「品がない」と批判し、物議を醸したこともありました。
私としてもあの時代、彼らが選択、”命懸け”で追求しファンが熱狂的に支持したスタイルを後出しで批判するのは気の毒な気がする反面、その創始者である三沢光晴さんの非業の最期を見た今では、どこかで軌道修正しておくべきだった、としか思えませんし、今なおこういうスタイルで試合を続けるのは、「もうやめとけ」としか言えないです。
大技の攻防、長時間試合することだけがプロレスの魅力じゃないのです。
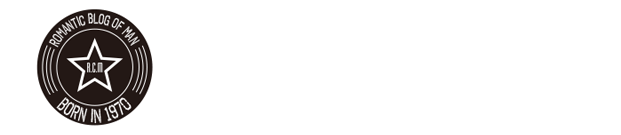
コメント